クラウドサーバーのコスト最適化とは?放置リスクから削減手法まで徹底解説!
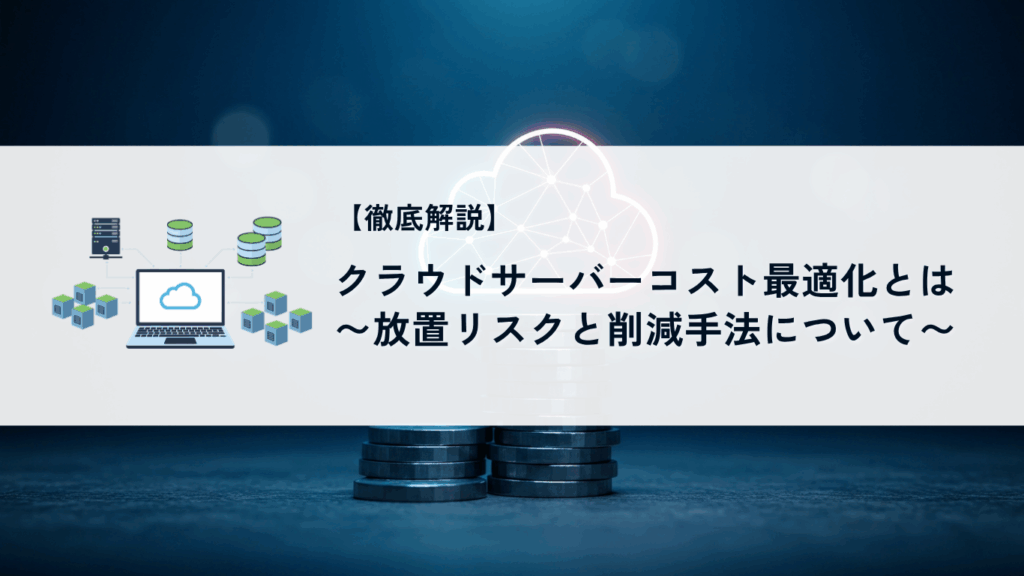
社会的な要請によって、企業のIT環境においてもサイバーセキュリティ対策とコスト効率を両立した運用が重要視されるようになりました。
しかし、多くの企業では「クラウドサーバーは導入したらそのまま放置」というケースが散見されます。
サーバーは「導入して終わり」ではなく、継続的な「運用と管理」が必要不可欠です。そこで今回は、クラウドサーバーの適切な運用方法とコスト最適化の手法について分かりやすく解説します。
目次
サーバーを放置するリスクについて
放置によるセキュリティリスク
レンタルサーバーであれば、サーバーのOSやミドルウェアの管理をベンダーに任せられるため、ほったらかしにしている人も多いです。しかし、クラウドサーバーについても放置していても動き続けることはありますが、以下の通り多くのリスクが潜んでいます。
- OSやミドルウェアのサポート切れ
- セキュリティホール(脆弱性)の放置
- システム障害の発生・長期化
- コンプライアンス違反
サーバーには車でいう車検のような法定の安全点検が義務付けられていません。そのため、意識的に管理しなければ放置状態が続いてしまいます。
実際に起こりうる被害事例
実際にとある病院で起きたサイバー攻撃によって、電子カルテが閲覧できなくなり病院機能が停止するなどのインシデントが過去に発生しています。また、このような事態になると企業のイメージの悪化やビジネスに直接的な損害をもたらします。
しかし、目に見えないリスクに対して危機感を持つ企業は決して多くなく、「うちの会社は大丈夫だろう」と過信し、同業他社で被害が発生するなど身の回りで事態が起きて初めてリスクを意識し始めることが多いので、被害が起きてからでは手遅れになるケースがほとんどです。
最適なサーバー環境とは
OSやミドルウェアのバージョンを常に最新に保つ
オペレーティングシステム(OS)やミドルウェアのバージョン更新は、サーバー管理の最も基本的かつ重要な要素です。
新しいバージョンでは、以前のバージョンで対策されていなかった脆弱性(セキュリティホール)を修正するためのセキュリティパッチが適用されていたり、システム全体の処理効率の改善や新機能が実装されている事があります。
また、更新することでリスク回避につながることも大きな要因です。古いバージョンでは、公式からの技術サポートが終了している(EOL: End-of-Life)場合があり、万が一バージョンに問題が発生しても公式なサポートを受ける事ができません。これは、セキュリティパッチも提供されなくなることを意味し、極めて危険な状態です。
ただし、OSの大幅なバージョンアップは、システム間の互換性の問題で新しいOSで動作しない事があったり、新しいOSの設定方法や構造が変化することによって稼働中のシステムが動かなくなるという課題があります。
そのため、まずは本番環境と同一の検証環境を作って事前テストを行い、データを段階的に移行させるなど計画的な更新を行うことをオススメします。
定期的な診断を行う
人間の健康診断と同様、サーバーにもセキュリティや稼働状況に関する定期的な診断が必要です。診断頻度に関しては、月1回の頻度で診断を受けている企業もあれば、全く行わない企業もあります。
理想的には定期的な診断が推奨されますが、「昨日は大丈夫だったけど、今日はダメ」という可能性もあるため、できれば毎日・リアルタイムでの監視や、緊急度の高い脆弱性への迅速な対応など、頻度が高いほど安心につながります。
コスト削減の実践手法
基本的なアプローチ
コスト削減を行う際の基本的な手順は主に4つです。
- 不要なサービスの停止:使っていないサービスや機能を確認し、起動していないかチェックし停止する
- スペックの見直し:リソース使用率を確認して過剰な性能(オーバースペック)を解消し、最適なサイズに変更する
- 契約形態の変更:長期契約や前払い契約(リザーブドインスタンスなど)で料金を安くする
- 安価なクラウドへの移行:よりコストパフォーマンスの良いサービスへの変更(またはサービス内のより安価なプランへの変更)
サーバーを構築したタイミングでは最適な環境でも、時間が経つにつれ使用しなくなった不要なサービスや、既存のサービスよりも更に性能の良いサービスがリリースされた、あるいはリソースが余っていて設定しているスペックを必要としていない場合など、現在の環境では最適ではない可能性があります。
また、当時は短期運用のつもりでもサービスが軌道に乗って長期運用が見込めることになれば、サーバーの契約形態を長期契約に変更することで、同じ環境でもコストをより抑えることができます。
さらに、利用しているクラウドサービス自体を見直し、より適した特徴を持つクラウドへ移行することもコスト最適化の1つの手段になります。
自社でできること
まずは、請求画面を定期的にチェックし、「どのサービスにいくら使っているか?」費用の内訳を把握する事が重要です。
定期的に請求画面を確認する習慣があれば、知らず知らずのうちに費用が上がっていたとしても、異常に気づくまでの期間を極力短くする事ができます。
また、普段のパフォーマンス(リソース使用状況)を知っておくことで、通常の範囲を超えた費用増加の異変にもいち早く気づく事ができます。
コスト見直しの現実
ただし、すべてのケースでコストが大幅に削減できるわけではありません。
すでにお客様自身で何回か最適化を試みている環境では、大きな削減を行うことは難しいです。
また、サーバーのスペックを下げる事で費用を抑えることも可能ではありますが、そのコスト最適化作業にかかる費用に見合った劇的な変化はあまり期待できません。
実際に依頼を受けて診断したところ、「もう既に最適化されていて、これ以上やりようがない」というケースもございます。ただし、このような場合でも、現状が最適であるという安心感と客観的な裏付けを得られるという価値があります。
まとめ
今回はクラウドサーバーのコスト最適化について解説しました。
サーバー運用においては、「運用管理を怠らないこと」と、「セキュリティとコスト効率のバランスを取ること」が重要です。放置によるリスクを理解し、適切な管理を行うことで、長期的な安定運用を実現できます。
今一度「サーバーの現在の状態は、本当に最適な状態なのか?」と精査を行い、新しい技術トレンドに沿った運用方法を検討することをオススメします。
サービスのお問い合わせ
ハイセキュリティ・ハイスピードを実現する「WordPress専用クラウドサーバー ウェブスピード」では、厳重なセキュリティ対策を実装しております。
自社のホームページも同サービス上で運用するなど、自社でも使っているサービスだからこそ、安心してお客様におすすめできる。という強みがございます。
サービスについて詳細をご希望の場合には、当サイトの問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
また、複雑化するクラウドコストをプロの目で分析し、最適なプランを提案・実施する「クラウドコスト見直し本舗」では無料診断も行っております。こちらも合わせてご検討ください。
